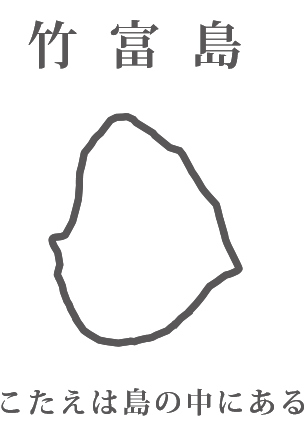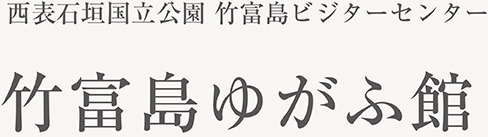令和7年度 竹富島の種子取祭
竹富島の種子取祭
由来:
種子取祭が、いつ頃始まったのかはわからない。
竹富島に人が住んで、農業を始めた頃に種子取祭が行われたとするならば、
種子取祭の始まりは12世紀頃と想定され、
それは今から900年前のことになる。
しかし、竹富島の農業の始まりがただちに種子取祭の始まりであると考えるのは早計であろう。
沖縄本島で行われていたタントゥイ(種子取)が、
八重山の島々にも伝わったと考えるのが妥当である。
とすると、種子取祭の始まりは、1500年のオヤケアカハチ事件前後のことであろうか。
はっきりした種子取祭の起源を知ることはできないが、
はじめの頃の種子取祭は、竹富島の6つの御嶽でそれぞれ祭りを行っていたと伝えている。
≪中略≫
「600年の歴史を有する種子取祭」という言葉をよく耳にするが、
それは種子取祭の由来伝承を根拠にしている。
種子取祭の由来伝承には、根原金殿をはじめとする六山の神々が登場しており、
その神々の時代は、およそ600年前のことであると想定して、
「600年の歴史」と伝えているのである。
― 全国竹富島文化協会編 『芸能の原風景』 より ―
詳 細:
種子取祭は、播種儀礼(良質な種子を選り分ける儀式という説もある)の祭ですが、
南島一円の島々で執り行われている祭祀です。
そのなかで竹富島の種子取祭(タナドゥイ)の特徴は、
粟の播種儀礼であること、戊子(つちのえね)を祈願の日と定めていることが挙げられます。
つまり、粟と戊子は、タナドゥイの象徴といえます。
令和7年度 竹富島 種子取祭の日程
(奉納芸能の2日間に明記している時刻は目安としてください)
・ 9月27日 (つちのと ゐ) シチマツリ (節祭)
古代の正月といわれる。新しい季節を迎えたことを神々に祈り、作物を育む大地と命の水(井戸)
に感謝する神事。古来より節祭から49日目の「つちのえね」の日を祭日とする
種子取祭に入るとされている。本年は、11月15日が“つちのえね”の日にあたり、
その日に種子を蒔く。それより4日前の“きのえさる”の日から種子取祭の日程に入る
とされている。
・ 9月29日 (旧暦8月8日) ユーンカイ (世迎い)
竹富島にニライカナイから訪れた神々によって、種もみがもたらされる神事が行われる。
1. 11月11日 (きのえ さる)種子取祭初日
初日はトゥルッキと称し、祭の計画手配を行う。玻座間、仲筋の両地区のホンジャー(長者)
に奉納芸能が尽くせるようにと祈願する
2. 11月12,13日,14日
種子取祭の諸準備。狂言、舞踊の稽古に充てる
3. 11月15日 (つちのえ ね)
神司はそれぞれの御嶽にてタナドゥイのウッカイ(ご案内)を行ったのち公民館役員と
合流して玻座間御嶽、世持御嶽、清明御嶽、根原屋などを廻り種子取祭の願いを行なう。
男生産人(18歳~69歳迄)は、早朝から幕舎張りなどの奉納芸能の舞台を設営する。
出欠を取り、理由もなく出役しない者には過怠金を科す。各家では種まき。
主婦はイイヤチ(飯初)作り。
4. 11月16日 (つちのと うし)
ンガソージといって、前日に蒔かれた種子がしっかりと土につくように、
精進を尽くす日とされる。家主がブママンガン・ブナルンガン(姉や叔母を神とすること)
を招いてイイヤチ戴みの儀式などもある。
また、この日はフクミといい芸能の稽古の総仕上げの日。
夜には公民館役員、石垣・沖縄・東京の各郷友会長などが
ブドゥイドゥン・キョンギンドゥンを訪ねて挨拶し激励する。
(午後5時15分 竹富公民館主催の種子取祭に関する講話がまちなみ館で開催)
5. 11月17日 (かのえ とら) ※ 明記している時刻は目安としてください
バルヒル願いの日、奉納芸能初日
● 午前06時30分頃
彌勒奉安殿には公民館役員、有志、三郷友会長などが弥勒興しの祈願
玻座間御嶽では神司の祈願
その後、両者は世持御嶽で合流し、バルヒルの願い、イバン取りの儀式がある。
場所を奉納芸能の舞台に移して、乾鯛の儀式が行われる。
● 午前08時00分頃 仲筋村主事宅へ参詣の儀式
● 午前10時00分頃 世持御嶽へもどる
● 午前10時45分頃 庭の芸能を奉納
棒術、太鼓、マミドー、ジッチュ、マサカイ、祝種子取、腕棒、馬乗者の順で行われる。
● 玻座間村(東集落・西集落)の舞台の奉納芸能が行われる。その順序は、(玻座間長者)、
弥勒、鍛冶工、組頭、世持、世曳狂言など。曽我兄弟で初日の芸能は終了
● 午後06時00分頃 イバン(九年母)戴みの儀式がある
それから世乞い(ユークイ)が始まる。ユークイは、種子取祭を統一した根原金殿を
まつる根原屋から始まり、その後三集落に別れてユークイが行なわれる。
・東集落 宇根屋、神司、主事宅を周り最後は宇根屋。
・西集落 神司、顧問宅を周り、最後は泉屋。
・仲筋村 生盛屋、神司宅、主事宅を回り最後は顧問宅。
6.11月18日 (かのと う) ※ 明記している時刻は目安としてください
● 午前05時30分頃 三集落のユークイの一団は、根原屋でユークイトゥドゥミを行う。
ユークイの儀式は全て終了。
● 午前06時30分頃 世持御嶽へ。イバンの返上を行う。二日目のムイムイの願い。
幸本フシンガーラの願い日とされ、それを祝して仲筋村のシドゥリャニが奉納され、
前日同様の乾鯛の儀式が行われる。
● 午前08時00分頃 玻座間村東集落主事宅へ参詣の儀式。
● 午前09時30分頃 世持御嶽へもどる。
● 午前10時00分頃 庭の奉納芸能(サチブドゥイと同じ)がある。
● 仲筋村の舞台の奉納芸能が終日行なわれる。その順序は仲筋村長者、弥勒、
シドゥリャニ、種子蒔狂言、天人狂言などがあり、最後は鬼捕りで奉納芸能は終了
● 午後05時頃 芸能の奉納はすべて終了
世持御嶽神前にて種子取祭首尾方の御礼を行う
首尾方の御礼を終えると男生産人は舞台ならびに供物小屋の片付け
7.11月19日 (みずのえ たつ)
男生産人は、早朝から幕舎片付け、経理係は祭の精算に取り組む。
● 午前10時00分頃 まちなみ館にて公民館役員・有志と三郷友会幹部との懇談会。
● 午後(時間未定) 支払議会を開催し、種子取祭の日程は総て終了する。
8.11月20日 (みずのと み)
種子取祭物忌(タナドゥイムヌン)。昭和24年に省略されたが、令和2年度以降、
竹富公民館発行の年間祭事行事表に掲載している。